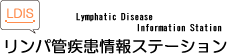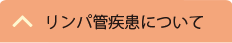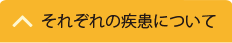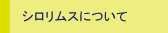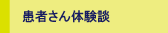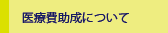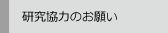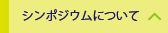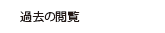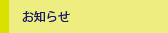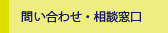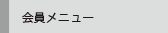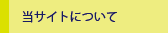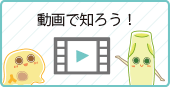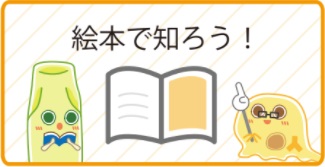リンパ管腫、リンパ管腫症に関して、良く訊かれる質問に対する回答です。
(記載されている内容は急速に進歩する医学の中で古い情報となってしまう可能性があります。可及的にアップデートを繰り返していきますが、お気づきの点はご指摘頂きますようお願いいたします。)
質問
 リンパ管腫の「病態」について
リンパ管腫の「病態」について
- リンパ管腫は悪性ですか?
- どれくらいの患者さんがいますか?
- リンパ管腫はどんどん大きくなっていきますか?
- 生まれる前にできるのですか?
- リンパ管腫が自然に小さくなって消えてしまうことはありますか?
- リンパ腫とリンパ管腫はどう違うのですか?
- 痛みはありますか?
- 親子で遺伝するのですか?
 リンパ管腫の「診断」について
リンパ管腫の「診断」について
 リンパ管腫の「治療」について
リンパ管腫の「治療」について
- リンパ管腫はどの科で診てもらえますか?
- 治療は必要ですか?
- どんな治療法がありますか?
- リンパ管腫は手術で取れるのですか?
- ピシバニールはどのようにリンパ管腫に効くのですか?
- ピシバニール治療は何回位行うのですか?
- インターフェロンは効かないのですか?
- ブレオマイシンは効かないのですか?
- 手術の危険はありますか?
- 治療後に残っている病変は放置してよいのですか?
 リンパ管腫の「予後」について
リンパ管腫の「予後」について
 リンパ管腫症の「病態」について
リンパ管腫症の「病態」について
- リンパ管腫症は悪性ですか?
- どれくらいの患者さんがいますか?
- リンパ管腫症はどんどん大きくなっていきますか?
- いつ発症しますか?
- リンパ管腫症が自然に治ってしまうことはありますか?
- リンパ管腫症とリンパ管腫はどう違うのですか?
- 親子で遺伝するのですか?
- ゴーハム病( Gorham-Stout病(症候群))はリンパ管腫症と同じですか?
 リンパ管腫症の「診断」について
リンパ管腫症の「診断」について
 リンパ管腫症の「治療」について
リンパ管腫症の「治療」について
 リンパ管腫症の「予後」について
リンパ管腫症の「予後」について
回答回答者:リンパ管疾患研究班
 リンパ管腫の「病態」について
リンパ管腫の「病態」について
- リンパ管腫は悪性ですか?
悪性ではありません。悪性腫瘍の持つ特性、「際限なく増殖する」「体の他の部分に飛ぶ」はありません。しかし周囲の組織に根を張るように広がっているため、切除するのが難しいことがあります。
(2025年5月29日) - どれくらいの患者さんがいますか?
国内では約10,000例の患者さんの存在が確認されています(厚労科研難治性疾患政策研究事業「難治性血管腫・血管奇形・リンパ管腫・リンパ管腫症および関連疾患についての調査研究」班)。
(2025年5月29日) - リンパ管腫はどんどん大きくなっていきますか?
何も治療を加えない場合、まれに自然に縮小していくこともありますが、一般的には体の成長とともに同じペースで大きくなると考えられます。
(2025年5月29日) - 生まれる前にできるのですか?
生まれる前にできることが多いと考えられています。病変部位が大きいときには、生まれる前にお母さんの超音波検査で発見されることもあります。
(2025年5月29日) - リンパ管腫が自然に小さくなって消えてしまうことはありますか?
全国調査によれば、外観上は10%以下の患者さんで消えていることが確認されています。
(2025年5月29日) - リンパ腫とリンパ管腫はどう違うのですか?
リンパ腫(悪性リンパ腫)はリンパ球という血球の腫瘍です。リンパ管腫はリンパ液を循環させるリンパ管という管が膨らんでいるもので、全くの別物です。
(2025年5月29日) - 痛みはありますか?
普段は痛みを伴いませんが、経過中に突然内部に出血を起こして急激に大きく腫れたり、細菌が侵入して赤く腫れたりすることがあり、そういう場合にはひどく痛みます。
(2025年5月29日) - 親子で遺伝するのですか?
遺伝しないと考えられます。世界的に見ても親子・兄弟での発症は極めて稀です。
(2025年5月29日)
 リンパ管腫の「診断」について
リンパ管腫の「診断」について
- リンパ管腫はどうやって診断するのですか?
腫れているところを触ると、特徴的な柔らかさを認めます。多くの場合画像検査により診断に至ります。超音波、CT、MRIなどの画像検査と臨床症状とを併せて診断することが多いです。
(2025年5月29日) - MRIは必要ですか?
MRIを行わずに診断できてしまうことも多いですが、様々な他の似たような腫瘤と見分けるため、また病変のひろがりを正確に知るために非常に役立ちます。
(2025年5月29日) - なぜエコーとCTの両方を行うことがあるのですか?
エコーで腫瘤の内部の様子はよく分かりますが、全体的な広がりなど、エコーでは見ることができないところもあります。また治療の経過を追うために全体の大きさを毎回同じ向きで比較するのに、CTは有益です。
(2025年5月29日)
 リンパ管腫の「治療」について
リンパ管腫の「治療」について
- リンパ管腫はどの科で診てもらえますか?
実際に治療を行うのは「小児外科」「形成外科」「耳鼻咽喉科」「皮膚科」がほとんどですが、部位により「消化器外科」「胸部外科」「整形外科」などで治療が行われることもあります。小児期の発症が多いため、「小児科」を受診した後にどちらかへ紹介されることが一般的です。
(2025年5月29日) - 治療は必要ですか?
悪性腫瘍ではなく、病変自体が命に関わることはありません。しかしながら、見た目に目立つため、運動の邪魔になるため、治療を希望されることが多いです。ほとんどの場合、緊急性はないので、治療の時期については担当の先生とよく相談してください。経過中に内部に出血したり、感染したりすることがあり、その際には治療を行うこともあります。また部位によっては、緊急に外科的な切除を必要とすることもあります(例えばお腹の中で大きくなり、食べ物が通りにくくなるとき。首にあって息をしにくくなるときなど)。
(2025年5月29日) - どんな治療法がありますか?
大きく外科的切除、硬化療法、その他に分けることができます。外科的切除はもっとも直接的で短期間で治療を終えられる可能性があります。硬化療法は硬化剤という薬を内部に注射します。硬化剤としては、国内ではピシバニール(薬剤名:OK-432)が、有効性が証明され保険でも承認されている薬剤として多く使われています。世界で比較的よく用いられている他の硬化剤として、ブレオマイシン(抗がん剤)、無水エタノール(アルコールほぼ100%の液体)、ポリドカノール、ドキシサイクリンなどがあります。
(2025年5月29日) - リンパ管腫は手術で取れるのですか?
病変が体のどこにあるのか、また、大きさや広がり方などが問題となります。 手足や体の表面近くにできている場合には完全切除できることがありますが、首からのどの奥の方に広がっている場合は、全てを切除することは難しい場合が多いです。全て病変を切除すると、そこを通る様々な神経・血管・筋肉を切除せざるを得ないため、機能的、美容的なバランスを考え、部分的に残す(部分切除)という選択をせざるをえなくなります。
(2025年5月29日) - ピシバニールはどのようにリンパ管腫に効くのですか?
2つの説があります。
(2025年5月29日)
ピシバニールは強い炎症を引き起こしますが、そのときに炎症細胞(白血球・リンパ球など)が出すサイトカインにリンパ管腫の内皮細胞(壁をつくっている細胞)が反応して、細胞と細胞の間に隙間を作ります。そこで嚢胞中のリンパ液が外に漏れ出て、嚢胞自体は小さくなる、という説。
嚢胞内でピシバニールに対する強い炎症が生じるため、同時に嚢胞の内皮細胞も傷害されてリンパ管腫が壞れる、という説。
いずれも完全に証明されてはいません。 - ピシバニール治療は何回位行うのですか?
嚢胞があって、それが小さくなれば全体として小さくなっていく、と考えられる限り、何回でも行えます。1回の治療で殆ど消えてしまうこともあります。病変が大きい場合には数回必要となることもあります。20回以上治療を受けている患者さんもいます。治療に対する反応は概ね良い(7-8割では満足が得られる)のですが、中には治りにくい患者さんもいます。ピシバニールを投与する間隔については決められた方法はありませんが、1回の治療効果が十分表れるのに、2-3ヶ月かかることもあるため、それを待つことが多いようです。(調査中)
(2025年5月29日) - インターフェロンは効かないのですか?
国内外でインターフェロンにより効果が見られたという報告もありましたが、効果は一定でなく、現在ではリンパ管腫にはほとんど用いられません。
(2025年5月29日) - ブレオマイシンは効かないのですか?
ピシバニールと同様に効果があります。ピシバニールが使われ始める前はもっとも効く硬化剤として選択されていました。肺線維症という副作用が起きる可能性があることもあり、日本では保険承認薬であるピシバニールを第一選択薬として使うことが主流です。
(2025年5月29日) - 手術の危険はありますか?
手術でリンパ管腫を切除するときには、周りの正常な部分も同時に切除せざるを得ないことが多く、機能的・美容的に問題を残すことがあります。特に顔や首の奥深くにある場合には様々の大切な神経や細かい筋肉を切除せねばならないこともあります。
(2025年5月29日)
手術の後には、切除した端からリンパ液が止めどなく流れ出てきたり、リンパ液が溜まって膨らみをつくったりすることもあります。また傷口や漏れてくるリンパ液を伝って細菌が入って感染を起こすことがあります。 - 治療後に残っている病変は放置してよいのですか?
硬化療法の結果もしくは外科的切除のあとで、まだ病変が残っていることは珍しくありません。ほとんど分からないほど小さくなって何年も経ってから、残った病変内に出血が起こって急に腫れたりすることは稀にあります。リンパ管腫が腫瘍として悪性化した報告はないので、生活上あまり支障がない場合には、残った病変に対して治療を行うかどうか、担当の先生とよく相談して考えるべきでしょう。
(2025年5月29日)
 リンパ管腫の「予後」について
リンパ管腫の「予後」について
- 最終的には治りますか?
病変の部位、大きさ、また嚢胞状・海綿状のタイプによります。全体としては8割の患者さんで消失もしくは縮小し、満足な治療結果が得られます。
(2025年5月29日)
一方、頚部・顔面の奥深くに広がるタイプのリンパ管腫は治療が難しく、治療の危険性を考えると治療を選択することもできず、長期にわたって大きな病変と付き合って行かざるを得ない患者さんもいます。 - 命にかかわることはありますか?
病変が頚部や縦隔(胸の真ん中部分)にあり、急速に気道を閉塞し、呼吸困難となることが経験されています。しかしながら、診断・治療が進んだ現在では、ほとんどの場合、そういった危険を避ける処置が早期になされています。
(2025年5月29日)
 リンパ管腫症の「病態」について
リンパ管腫症の「病態」について
- リンパ管腫症は悪性ですか?
腫瘍ではなく、悪性疾患には分類されていません。しかし、リンパ管腫と違い、全身の骨や肺などの多臓器に異常なリンパ管組織が増えていきます。病状が進行すると命に関わる場合もあります。
(2025年5月29日) - どれくらいの患者さんがいますか?
非常に珍しい病気で、国内では100例程度と推定されます。
(2025年5月29日) - リンパ管腫症はどんどん大きくなっていきますか?
病変が広がり、新たな症状がでてくることもあります。中には、発症してから急激に進行する方もいれば、症状が自然に良くなったり、悪くなったりを繰り返す場合もあります。
(2025年5月29日) - いつ発症しますか?
どの年齢でも起こりますが、調査では8割の患者さんは小児期に発症していました。
(2025年5月29日) - リンパ管腫症が自然に治ってしまうことはありますか?
自然に改善する場合もありますが、通常は治癒することはありません。
(2025年5月29日) - リンパ管腫症とリンパ管腫はどう違うのですか?
リンパ管腫症は全身の骨や肺、肝臓、脾臓などの臓器に異常なリンパ管のかたまりができる病気です。リンパ管腫は一部分のリンパ管が異常に膨らむ病気です。病変は、一つながりで多発することはまれです。例えば、リンパ管腫は頚部に多く見られます。
(2025年5月29日) - 親子で遺伝するのですか?
遺伝しないと考えられています。
(2025年5月29日) - ゴーハム病( Gorham-Stout病(症候群))はリンパ管腫症と同じですか?
ゴーハム病( Gorham-Stout病(症候群))はリンパ管の異常な組織とともに進行性に骨が融解する病気をいいますが、リンパ管腫症と同じように乳び胸を合併することもあり、共通点が多い病気です。それぞれの原因が明らかになっておらず、異なる疾患としています。
(2025年5月29日)
 リンパ管腫症の「診断」について
リンパ管腫症の「診断」について
- リンパ管腫症はどうやって診断するのですか?
非常に珍しい病気なので、診断は難しいといわれています。原因不明の骨融解や乳び胸など、リンパ管腫症に特徴的な症状があった場合に、検査を進めます。確定診断のため、骨病変などを手術で採取し、病理検査をする場合もあります。類似した他の病気と鑑別する必要があるため、臨床症状および画像所見、病理組織学的所見から総合的に診断することが重要です。
(2025年5月29日) - CTは必要ですか?
CTはX線で分かり難い骨病変や、肺の病変を探すのに有用です。しかし、被爆の問題もあるため、MRIなど他の検査を行うこともできます。
(2025年5月29日) - リンパ管シンチグラフィは何をするのですか?
放射性医薬品を体内に投与するとリンパ管に取り込まれます。シンチグラフィの装置を用いて取り込まれた放射線医薬品が体内でどのように分布しているかを調べることで、リンパ管の走行や体内の循環を見ることができます。
(2025年5月29日)
 リンパ管腫症の「治療」について
リンパ管腫症の「治療」について
- リンパ管腫症はどの科で診てもらえますか?
小児期に発症することが多いので、まず小児科が入り口となることが多いですが、リンパ管腫症は全身にできる病気なので、病状によって様々な診療科が担当になります。骨に病気があれば、整形外科でみてもらいます。肺や乳び胸などで手術が必要な場合は、小児外科や胸部外科です。成人の患者さんでは、内科を中心として、やはり小児と同様に様々な診療科が担当となっています。
(2025年5月29日) - どのような時に治療が必要ですか?
多くの場合は困った症状があるため、何らかの治療を必要とすることが多いですが、症状はなく偶然病変が見つかった場合など、病状によっては自然に経過をみる場合もあります。
(2025年5月29日) - どんな治療法がありますか?
病気の程度や部位によって様々です。たとえば、骨の局所病変に対しては、外科的切除や放射線治療、硬化療法などを行うことがあります。様々な症状を改善させるシロリムスの内服治療が優先的に行われるようになっています。インターフェロンやビスホスホネートを全身投与する場合もあります。胸水に対して胸腔穿刺、胸膜癒着術、胸管結紮術、放射線治療などを行います。また食事療法(脂肪制限食、高カロリー輸液、中鎖トリグリセリド)を行うこともあります。薬物が有効であったという報告もあります。
(2025年5月29日) - リンパ管腫症は手術で治るのですか?
手術だけで治すことは難しいことが多いと考えられます。難しい症状のひとつである乳び胸に対しても様々な手術を行い、治療効果があることもありますが、治癒困難なこともあります。
(2025年5月29日) - 薬で治るのですか?どんな薬を使いますか?
病気の原因は今の時点ではよくわかっていませんが、全身に血管やリンパ管が増殖する病気なので、これらを抑える薬を使い、有効な場合があります。現在では、シロリムスが第一選択として用いられます。他にインターフェロンやサリドマイド、プロプラノロール、べバシズマブ、抗がん剤などの報告があります。海外では多くの治療を試されていますが、効果はまちまちで、今のところは決定的な治療はありません。また小児に安全性が確立されていない薬もあります。
(2025年5月29日)
 リンパ管腫症の「予後」について
リンパ管腫症の「予後」について
- 最終的には治りますか?
病気の部位や程度によってことなります。一時的に良くなっても再発する場合もあります。原因が明らかでないため、完全に治すことが難しいのが現状です。
(2025年5月29日) - 命にかかわることはありますか?
中には、乳び胸が悪化して命に関わることがあります。骨だけであれば、通常は命には関わりませんが、場所によってはあり得ます。
(2025年5月29日)